キングダムの中でも屈指の大戦として描かれているのが「函谷関の戦い」です。
趙・魏・楚・燕・韓の五国が連合して秦を攻め込むという、まさに中華全土を巻き込む大戦。
そのスケールの大きさと、数々の名将たちの激突が読者の心を掴みました。
初めて読んだとき、戦場の空気の重さに圧倒されたのを覚えています。
ページをめくる手が止まらず、まるで自分も戦の中にいるような感覚でした。
この記事では、函谷関の戦いの概要や登場人物の最期、そして史実との違いについて掘り下げていきます。
それでは最後までお読みください(^▽^)/
「キングダム」函谷関の戦いとは
もし本当に辛い事があったらキングダムを思い出してください。函谷関の攻城戦をさせられる兵の方が絶対に辛いのでそれに比べると大体の事が小事に思えます。 pic.twitter.com/77OWGZ1xFo
— (株)おくりバント会長 高山洋平 (@takayamayohei1) February 4, 2024
函谷関の戦いは、秦に対抗するために他の五国が結束した連合軍との大規模戦争です。
舞台は秦の国境に位置する要衝「函谷関」。
地形的に守りやすく、古くから防衛拠点として知られていました。
物語の中では、各国の思惑と策略が複雑に絡み合い、戦略の応酬が続きます。
初めてこのエピソードを読んだとき、ただの戦ではないと感じました。
単に敵と味方がぶつかるのではなく、「国の理想」「将軍の誇り」「仲間を信じる心」がそれぞれの軍の中で火花を散らしています。
特に秦側の布陣は圧巻で、王翦・騰・蒙武・桓騎といった猛将が揃う戦いは見ごたえがありました。
秦の布陣と連合軍の策略
秦軍の中心となるのは、総大将・蒙驁。
そして副将として王翦、桓騎、騰が配置されました。
それぞれが異なる戦い方を持ち、まさに個性のぶつかり合いでした。
王翦は冷徹な知略型、桓騎は予測不能の奇襲型、騰は安定感と冷静さを兼ね備えた実力者。
三者三様の戦術が、戦場の流れを見事に変えていきます。
一方、連合軍の指揮を執ったのは魏の呉鳳明。
知略に優れた呉鳳明が中心となり、楚の汗明や韓の成恢、趙の慶舎などが集結します。
これだけの強者が一堂に会する戦は、キングダム全体でも異例の迫力でした。
読んでいて思うのは、誰もが「自分の国を守るため」に戦っているということ。
敵味方の境界があるのに、それぞれの信念に共感してしまうのがこの戦いの魅力です。
「キングダム」函谷関の戦いで死亡した武将たち
キングダム、函谷関のコレ最高に好き pic.twitter.com/uUJ3nABMJD
— 禁酒のプロ™️ (@Heil_Teufelmin2) March 2, 2024
ここでは、合従軍編で命を落とした武将について、できるだけ深く掘ってまとめます。
単に「死んだ」という事実ではなく、その場面がどんな意味を持っていたのか、誰に何を託して散ったのか、戦局にどう響いたのか、そのあたりまで踏み込みます。
なお、合従軍編=函谷関の戦い〜蕞防衛戦(秦が六国連合に攻め込まれて国として危なかったあの一連)として扱います。
まずは秦側からいきます。
秦側で死亡した武将・兵たち
秦の側は「守る戦い」だったので、味方の犠牲は重いです。
特に前線を押さえ続けた古参や、消耗が激しい部隊から死者が出ています。
麃公(ひょうこう)
合従軍編で最も衝撃を与えた死のひとつが麃公の戦死です。
麃公は本能型と呼ばれるタイプの大将軍で、理屈ではなく「戦場の匂い」で勝機を嗅ぎ分ける将。
乱軍をまとめて一気に押し潰す突破力が異常に高い武人です。
合従軍が秦に攻め込んだ際、李牧は麃公を狙い撃ちにし、龐煖との強制的な一騎打ちに追い込みます。
龐煖は“武の極み”を目指す存在として描かれる化け物級の武将で、ただの刺客ではなく「人の形をした天災」に近い存在。
その龐煖との戦いで、麃公は片腕を斬り落とされ、肉が裂けても地面に倒れても、なお立ち向かいます。
ここで重要なのは、麃公が最後まで「秦を守る」ではなく「信じた火をつなぐ」ことを優先したことです。
麃公は死の寸前、信の目をまっすぐ見て「火を絶やすではないぞ」と言い残します。
ここで言う“火”は、単なる士気とか根性ではなく、未来の秦の中核を担う若い武人たちの戦意そのものです。
この瞬間、信はただの有望株から「託された者」に変わります。
戦場の世代交代が、言葉ひとつで起きるのがキングダムのすごいところだと感じました。
麃公の死は、秦軍にとっては痛恨の損失である一方、飛信隊や蒙武軍にとっては「撤退ではない、生存だ。生き残ることで勝ちへつなげる」という共通認識を生みました。
つまり、武力としての麃公はここで消えるけれど、意思としての麃公は飛信隊の中に生き続ける構造になっているんです。
張唐(ちょうとう)
張唐は、いわゆる“古き秦”の象徴です。
老将で、泥臭くて、国に骨を埋める覚悟を最初から持っているタイプ。
合従軍戦では韓軍の大将・成恢が毒を使った戦術で秦軍を削りに削ってきます。
あの毒は正面からまともに受けると、じわじわ兵ごと腐らされるレベルの凶悪な兵器。
まともにやっていたら秦軍の一角がまるごと沈むところでした。
そこで張唐が毒に侵されたまま成恢の本陣に突っ込み、満身創痍のまま成恢の首を落とします。
もうこの時点で張唐の身体はほとんど限界です。視界も体温もおそらくおかしい。
なのに最後の最後まで武人の目をしている。
この戦果はデカいどころではありません。
成恢の死によって韓軍は一気に機能不全になり、韓側の攻勢そのものが止まるからです。
つまり張唐の死は「大将一人の死」ではなく、韓軍の“武器ごと”止めた一撃でした。
張唐はその直後、桓騎に向かって「秦国一の武将になれ」と言い残します。
このセリフ、読み返すとすごく苦いんです。
なぜなら桓騎は、秦の正統派とは正反対のやり方をする野盗上がりの将。
つまり張唐は、自分が生きてきた「まっすぐな秦」とは別ルートの“これからの秦”を認めて散ったとも読める。
ここで桓騎は、ただのダークホースから「期待を背負わされた存在」になるんですよね。
桓騎のその後のやり方(冷酷極まりない戦術や大量虐殺的な殲滅など)が、全部正しいなんて言いませんけど、張唐の死を踏み台にしてることは事実なんです。
だから桓騎という存在は、すでに誰の血も背負って動いている。
そこが人間として恐ろしくて魅力的でもあります。
蒙驁(もうごう)軍・古参の犠牲
蒙驁は秦軍の総大将のひとりとして函谷関側で奮戦しますが、蒙驁そのものはこの合従軍戦の中で命を落とすわけではないにせよ、蒙驁軍の古参兵はものすごい勢いで削られます。
ここは単行本でさらっと流れるように描かれる場面も多く、逆に読者側が見落としがちですが、あえて言いたいのは「名も出ない兵の死」が秦軍にとっては本当に重いということ。
函谷関という防衛拠点を守る戦は、基本的に“耐える戦”です。
突撃して名を上げるチャンスが少ないぶん、ただ耐えて死ぬ兵が増える。
名も出ない兵の死体が積み上がっていく描写こそ、合従軍編が「国が死ぬかもしれない戦い」だとわからせる説得力になっていました。
こういうところ、ものすごく生臭いのに、目をそらせないんですよね。
蕞(さい)防衛戦での市民兵の死
合従軍戦の終盤は、蕞での籠城戦に至ります。
ここはもはや「秦軍の戦い」というより「秦そのものの戦い」です。
王都から離れた辺境の小都市・蕞が最終防衛ラインになってしまい、成人していない若者や老人まで武器を持たされる。
蕞の戦いでは、名も知られていない蕞の住民が次々と倒れていきます。
漫画としてはメイン武将の死亡ほど派手に扱われていないものの、精神的インパクトは正直そっちの方が重いです。
普通の民が「国の存続」と引き換えに命を差し出す展開って、冷静に考えるとかなりエグい構図です。
蕞防衛戦は、政が直接前に出て鼓舞することで持ちこたえますが、裏を返せば、それほどまでに死者が出ているということでもあります。
蕞で立ち上がった名もなき兵の死は、後の秦の統一にとって「国の土台」そのものになっています。
これを死者カウントに含めないのはむしろ失礼だと思うので、あえてここに入れました。
合従軍側(敵側)で死亡した武将・大将級
合従軍編は「五国連合軍」として秦に襲いかかったわけですが、連合軍側も決してただの悪役ではありません。
それぞれが国の未来のために命を張っており、負けた側にも胸を張る理由がある。だから印象に残るんです。
成恢(せいかい)
韓の大将・成恢は、毒戦術のスペシャリスト。
毒を霧状に撒くことで、戦場そのものを殺すという最悪の戦術を使います。
成恢のすごいところは、単なる残虐性ではなく「国のためならどんな手でも使う」という愛国の方向に全振りしている点。
きれいごとを投げ捨てて韓を生き延びさせようとしていた、とも言えます。
つまり成恢は“卑劣な戦術家”というより、“国の存続のために手段を選ばない男”という側面も持っている存在。
張唐はそんな成恢に真正面から挑み、毒でボロボロにされながら首を取ります。
この討ち取りは象徴的です。秦の古参の老将が、韓の狂気の技術者を倒して、ともに地に伏す。
美化すれば「古き時代の決着」みたいに言ってもいいくらいの重さがあります。
成恢の死で韓軍は壊走し、合従軍の一角が崩れる。
つまり一人の死で前線がまとめて折れたわけです。
これは合従軍全体にとって計り知れない痛手でした。
汗明(かんめい)
楚の雷鳴のごとき大将が汗明。
汗明は力押しの暴力装置というだけではなく、「中華最強」を自称するだけの根拠を持つ巨人として描かれる存在でした。
蒙武との一騎打ちがまさに合従軍編の「武のピーク」です。
汗明は全身でぶつかり、蒙武は全身で受けて返す。
互いが互いを正面から叩き潰そうとする、あの泥臭くて血の匂いがする戦いは、読んでいる側の肩や首が無意識に固まるくらいの迫力があります。
結果、汗明は蒙武に討たれる形で戦死しますが、あの死はただ負けただけでは終わっていません。
汗明が倒れた後の楚軍の顔、あれがすべてを物語っていると感じました。
絶対的な柱が崩れた時の空虚さ。
士気だけではなく、存在意義そのものを失ったような虚脱。
汗明の死は、楚軍だけでなく合従軍全体の流れを鈍らせました。
楚の突破力が落ちるということは、秦への圧力が一段下がるということ。
つまり秦が呼吸できるようになる。
汗明の死は「秦が一回息を吸えるようになった瞬間」だったと言っても大げさじゃないと思います。
廉頗級の猛将はこの局面にはいないものの、趙側の将や、魏側の指揮官級にも多数の死者が出ています。
特に慶舎(けいしゃ)サイドは、飛信隊の動きに絡んで激しく削られ、慶舎自身も後に信に討たれる運命へと流れ込んでいきます。
慶舎は合従軍戦そのものでは命を落としませんが、この戦いで信と飛信隊が慶舎に「刃が届く距離」に上がってきたのは事実で、つまり合従軍編は慶舎の死のプロローグでもあるんです。
この観点は意外と語られないので、あえて触れておきます。
龐煖(ほうけん)側の被害
龐煖はここで死なないものの、龐煖の存在そのものが「味方にも犠牲を強いる」性質を持っています。
龐煖が麃公を仕留める過程では、周囲はほぼ“龐煖と麃公の舞台装置”と化し、そこに巻き込まれるかたちで有象無象が倒れていく。
このあたりは「龐煖は人を救う存在なのか、奪う存在なのか」という問いを強く意識させる場面でした。
龐煖は「武神」を自称する存在なのに、やっていることは何百人もの命を踏み台にすること。
その矛盾が強烈に焼き付くのが麃公戦です。
蕞の戦いで散った無名の兵と住民
これはどうしても書きたい。
趙軍が蕞に殺到したとき、蕞はもともと軍事都市でもなんでもなく、農と生活の町です。
そこに、政が自ら赴き、城壁の上から「この場に立っているすべては秦の盾だ」と鼓舞する。
このシーンでは名のついた将軍の死よりも、名前すら与えられず倒れていく住民兵の姿が延々と描かれる。
読みながら息苦しくなった読者も多いはずです。
合従軍編は、将軍の見せ場ばかりが話題になることが多いですが、実際のところ「秦が一つの国として生き残るために、王都から遠く離れた市井の人間が血を流した」という、ものすごく泥くさい現実を見せています。
蕞は最終的に踏みとどまり、秦は滅亡を免れます。
つまり、蕞で死んだ民兵は秦を一度救った、と言っていい。
合従軍と秦の国力勝負だったはずが、最終的には“どの国がより生き延びたいと本気で思っているか”の勝負になっていた。
蕞はその象徴です。
「キングダム」函谷関の戦いと史実の違い
キングダムでお馴染みの函谷関。こちらは秦ではなく漢の時代のもの。洛陽から車で40分ほど。世界遺産のシルクロードの構成遺産。要塞というよりは関所感が強そうですね。 pic.twitter.com/zIQiVJHFEL
— Asia Strategist (@yoichiro_416) June 12, 2021
函谷関の戦いは、キングダム全体の中でも「秦という国が本当に滅びるかもしれない」という感覚を読者に突きつけてくる大きな山場です。
しかもこの戦い、ただ派手だっただけではなく、史実に触れている部分と、漫画ならではの脚色が入り混じっていて、その境目がかなり面白いところなんですよね。
ここでは、キングダムの函谷関の戦いが史実のどんな出来事をベースにしているのか、そしてどこが変えられているのかを、できるだけ丁寧に掘っていきます。
まず大前提として、キングダムは「史実を骨格にして、物語としての説得力を持たせるために肉付けしている作品」です。
だから完全再現ではないし、完全フィクションでもない。函谷関の戦いはその典型です。
函谷関は古代中国における要衝です。
関、つまり関所のこと。
黄河の南側、いわば秦の東の玄関口にあたる重要な防衛線でした。
「東から侵入してくる敵をここで止める」ための門、という表現がいちばん近いと思います。
秦は西方の国なので、東側には韓・魏・趙といった強国が並んでいます。
逆に言うと、函谷関を突破されるということは、敵が秦の腹に直接ナイフを突きつけられる状態になる、ということなんです。
史実でも函谷関は何度も名前が出ます。
春秋戦国の時代を通して、東西の境目として何度も争点になった場所で、守る側からすると「ここを落とされたら国が終わる」。
攻める側からすると「ここをこじ開ければ秦に刃が届く」。
そういう意味では、キングダムが函谷関を“国家の喉元”として描くのはかなり正しい空気感だと感じます。
ただし、史実の函谷関の戦いはキングダムで描かれたような「五国連合が一斉に押し寄せて、秦が壊滅寸前」という形では残っていません。
ここが大事な分岐点です。
キングダム版「函谷関の戦い」とはどんな戦いだったのか
キングダムの世界で描かれた函谷関の戦いは、簡単にいうと「趙・魏・楚・燕・韓の合従軍が秦を滅ぼしにかかる」という大連合戦です。
いろんな国の大将級が一気に秦に押し寄せ、函谷関という要塞をめぐって殴り合う。
しかもただの正面決戦じゃなく、それぞれの国がそれぞれのやり方で秦を削りにくるので戦線が同時多発的に炎上する、という構造になっています。
例えば、魏は呉鳳明の高度な兵器と戦術で正面突破を狙う。
楚は汗明の圧倒的な膂力と兵力で力押ししてくる。
韓は成恢の毒という人間兵器みたいなやり方で秦軍を内側から腐らせる。
趙は李牧の読みと分断策で決定打の環境を整える。
これらが同時進行で秦を襲う。読んでいると「秦、詰みでは?」と思うくらいの総攻撃です。
この構成は、はっきり言ってフィクション寄りです。
史実にそんな“中華オールスター決戦”のような合従軍バトルがあったかというと、そこまでは確認されていません。
もちろん「合従」という概念は実在します。
複数の国が秦に対抗して同盟を組み、一斉に秦を叩こうとする動きは、戦国七雄の時代では何度も繰り返されています。
つまり「複数の国が秦に連携して襲いかかる」という発想は史実にある。
だけど「五国がここまで組織的に、ひとつの戦場で同時に秦を潰しにきた」という描き方は、物語としての脚色の度合いが強い、ということです。
この脚色は大げさというより、狙いがはっきりしています。
秦って国がどれだけ恨まれているか、どれだけ危険視されているかを、読者に一撃でわからせるためです。
「あ、全員が本気で潰しに来てるんだな」と感じさせるために、各国の代表的な将軍が勢ぞろいする形になっているわけです。
史実における合従と、キングダムの合従軍はどこが違うのか
史実の「合従」というのは、ざっくり言えば“対秦包囲網”です。
秦が頭一つ抜けて強くなってきた結果、他の国が「このままだと一国ずつ順番に潰されるぞ」という危機感を共有し、「一回みんなでまとまって先に秦を叩こう」という動きが出る。
この思想そのものは、歴史的に何度も試されました。
ただ、史実における合従は、思っているほど上手くいっていません。
国同士の利害がバラバラすぎるからです。楚は楚の事情があり、趙は趙の領土が喉から手が出るほど欲しい地域があり、韓や魏はすでに疲弊しているので本音では長期戦に耐えられない。
だから史実では、各国が手を組むと言いつつも、いざ戦いになると「うちの兵はあまり損耗させたくないので、そっちが前に行ってくれ」という政治的な牽制が発生する。
簡単に言えば、全員が自分以外に血を流させたいんです。
キングダムはこの“まとまらなさ”というリアルをある程度踏まえながら、同時に「いや今回は本気でまとまったんだよ」と宣言するために、わざと一箇所=函谷関に全勢力を集めています。
実際の歴史では、秦への圧力は複数の場所で同時並行的に発生するのが普通なんですが、漫画としては戦場を一つに集約した方がわかりやすいですし、読者としても「この戦いで秦が終わるかどうか」が一目でわかる方が熱いんです。
つまり史実が全方位的・政治駆け引き的な圧迫なのに対して、キングダムはそれを一枚の巨大な戦場にまとめ直し、軍神クラスをすべて同卓させている。
そこが最大の違いです。
秦側の将軍配置の違い
キングダムの函谷関では、秦の防衛戦力として蒙驁、王翦、桓騎、騰、蒙武といった大物が同時に動きます。
読んでいて胸が躍る布陣です。
一方で史実では、このラインナップが「同じタイミングで肩を並べて戦った」という明確な記録はありません。
史記などに残っている史料を見ると、それぞれは確かに秦の重鎮ですが、活躍時期や主戦場がズレている場合も多いです。
特に桓騎の扱いはキングダム的です。
桓騎は史実にも登場する武将で、趙を相手に大戦果を挙げていますが、異様に残虐なやり方で勝利をもぎ取るという特徴が強調されるのは、かなり「キングダムの文脈」の味付けが濃い部分です。
函谷関編では、桓騎は「ならず者の天才」という役割を与えられます。
正攻法では絶対に勝てない敵を、ルールを無視する残酷な発想で崩す役。
これって、実は秦という国の二面性を象徴しているんですよね。
秦は“正統的な戦術国家”でもあるけれど、“手段を選ばないモンスター国家”でもある。
その両方を一つの戦に詰め込んで見せるために、桓騎の存在が使われている。
史実の配置というより、国家のキャラづけのための配役だと言えます。
また、蒙武と汗明の一騎討ちも「漫画だからこそ全部見せる」構成です。
史実では大将級が正面から一騎討ちして、それで戦の大勢が決まるというのは、かなりドラマチックな表現の領域に入ります。
実戦で大将同士が殴り合うなんて本当にあったら国が震えるレベルの損害なので、普通は護衛と本陣の兵が文字通り命張って止めます。
でもキングダムはあえてやる。
この一騎討ちを“合従軍編の武”の頂点に据えて、「結局のところ、どの国が一番デカい牙を持ってるのか白黒つけようぜ」というわかりやすい形に落とし込んでいます。
このわかりやすさは史実よりもマンガ的。
でも、そのマンガ的表現で、当時のパワーバランスの本質(楚は化け物級の武力を抱えていた、秦はそれに正面で勝てる怪物も抱えていた)を説明することに成功している、という感じなんです。
史実では“函谷関を抜かれたら秦が終わる”という認識はどれくらいリアルだったのか
これはかなりリアルだった、と言っていいと思います。
秦が統一の一歩手前まできていた時代、周囲の国からすれば「このまま好き放題やらせたら全部飲み込まれるわ」という恐怖がある。
その恐怖が合従という形になって秦を囲みにいく。
だから、秦の側も東側防衛ラインで踏みとどまる必要があった、という構図そのものは歴史的な手触りがあるんです。
秦は基本的に、「攻めていく国」というイメージが強いですけど、当然ながら守らなきゃいけない局面も何度もあった。
その代表例として函谷関が選ばれているのは、かなり理にかなっています。
さらに言うと、秦にとって函谷関は軍事だけでなく心理の境界線でもありました。
もし函谷関を突破されて咸陽に迫られるようなことがあれば、秦の諸侯や豪族層が動揺して、内側から瓦解する恐れもある。
つまり「外敵が攻めてくる」という以上に「味方の信頼が揺らぐ」。
ここまで来られたら終わり、というメンタル的なラインにもなっていたわけです。
キングダムはその“精神的なラストライン”を、読者にも可視化させています。
「ここで負けたら終わり」っていう緊張感を共有できる位置づけにしてあるので、史実の地政学的な意味づけをドラマ化するのにすごく上手い使い方をしていると言えます。
死亡者・戦死描写はどこまで史実寄りなのか
ここも重要です。
キングダムの函谷関の戦いでは、多数の名将級が命を落とします。
韓の成恢、楚の汗明など、「国の看板」として描かれた猛将がばんばん死にます。
史実では、もちろん大物の将が討たれることはありますが、何人ものトップ級が同一会戦で次々に死亡、というのはそう簡単には起こりません。
特に楚の大将クラスがああいう形で討たれるのは、かなり劇的な描き方です。
つまり、死亡ラッシュはマンガ的な誇張なんですが、これも単に盛っているわけではありません。
意味があってやっている。
何かというと、「この戦いで秦が生き延びられなかったら、この先の歴史そのものが変わっていたんだぞ」ということを、わかりやすく読者に叩きつけるためです。
- 汗明の死=楚の矛が折れた。
- 成恢の死=韓の毒戦術が止まった。
- 張唐の死=秦側は血を吐いてでも勝ち筋を残した。
- 麃公の死=秦の次世代に火が渡った。
これらは、史実の「戦役の結果と影響」を、武将の命という形に凝縮して見せる演出なんです。
歴史的にいえば「この戦のあと、秦は立て直した」「楚は勢いを落とした」という話を、キングダムは「この人の死で流れが変わった」と人格化する。
だから心に刺さる。
一番大きい違い:戦いの“単発化”と“物語化”
史実はもっと長い。
対秦包囲網は何度も起きるし、秦も何度もはねのける。
その積み重ねの先に中華統一がある。
でもキングダムでは、それらの圧力を「合従軍編」という巨大な塊にして、ひとつの生死線にまとめてある。
すると、読者としても「ここが山場だ」とはっきり感じられる。
これが物語としての大きな強みです。
言ってしまえば、史実のダラッと続く国際政治と軍事圧力を、キングダムは“函谷関の死闘”という一本のナイフに削っている。
そのぶん刃先は鋭いし、感情も乗る。
その代わり、現実よりもドラマ的。
この交換はすごくわかりやすいし、秦という国が「ひとつの物語の主人公」として立ち上がる瞬間でもあります。
函谷関を生き延びることが、秦という国の“キャラ立ち”なんです。
つまり、キングダムの函谷関の戦いは、歴史をそのまま描いたものではないけれど、秦という国がなぜ中華統一まで走り切れたのか、その精神的リアリティを読者に伝えるための“圧縮表現”なんです。
秦がどれだけ狙われていたか。周囲がどれだけ本気で潰しにきていたか。
秦がどれだけ血を吐いて生き残ったか。
それを一撃で理解できるようにしたのが、キングダム版・函谷関の戦いの姿なんだと思います。
まとめ
キングダムの函谷関の戦いは、秦の運命をかけた大戦であり、史実をベースにしながらも大胆な演出が加えられています。
戦場で散った武将たちの死が無駄ではなく、次の世代へと繋がっていく描き方に深い余韻が残ります。
史実では小規模だった戦を、ここまで壮大に描けるのはキングダムならでは。
蒙武の拳、王翦の知略、桓騎の狂気、騰の冷静――その全てが秦という国を形づくっているように感じます。
何度読み返しても新しい発見があり、読むたびに「命を懸けて戦うとはどういうことか」を考えさせられます。
函谷関の戦いは、ただの戦闘シーンではなく、キングダムという作品の魂そのものかもしれません。
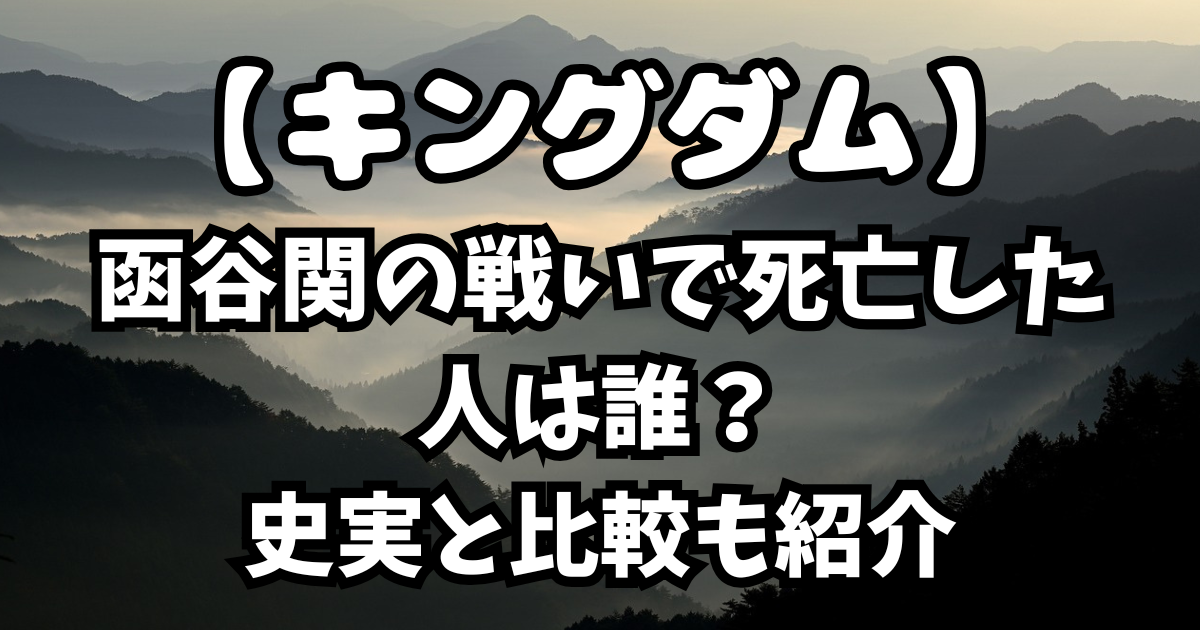


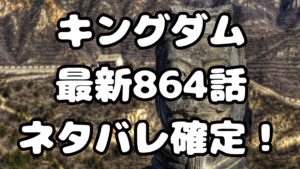
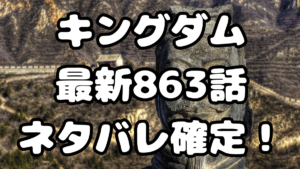
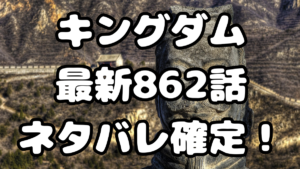
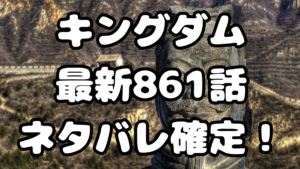
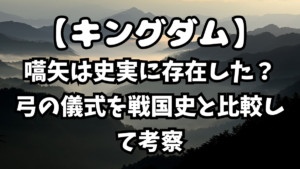
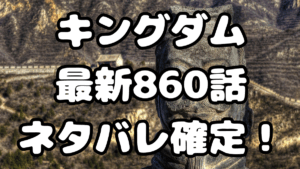
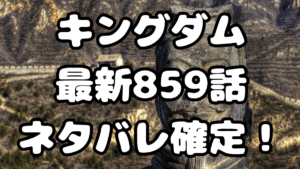
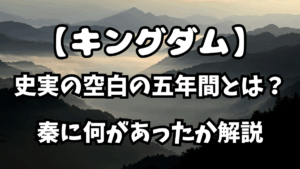
コメント