「キングダム」を読んでいて、昭王という存在に不思議な印象を持つ人は多いと思います。
王としての登場は短いのに、作中ではまるで伝説のように語られる。
では、史実の昭王はどんな人物で、漫画ではどう描かれているのか。
そして、昭王の死後、なぜ秦は一気に中華最強の国へと駆け上がったのか。
史実の秦と「キングダム」の秦を並べて見ると、ただの戦記漫画では語りきれない改革の重みが見えてきます。
ここでは、昭王の時代から死後の変化、そして漫画版との違いを交えて、秦がどうやって最強になったのかを掘り下げていきます。
「キングダム」史実の昭王とは?
2週間ぐらいかけて「昭王〜大秦帝国の夜明け〜」を観ましてん。
長平の戦いの解釈がキングダムとは違って面白かった。白起かっこいいけど可哀想やし、范雎めっちゃ嫌なやつやし、昭王がクソヤローやけど、嬴政の天下統一の礎になったんやと思うと複雑。
実際のとこ、どーやったんかしら… pic.twitter.com/YO52uo4mWo— 中西とか金魚とか玖蘭とかQ_laとか (@kingyo0119) December 24, 2021
史実の昭王は、秦の歴代の王の中でも異質な存在です。
武力で名を上げたわけではなく、国の仕組みを整えた王でした。
紀元前306年から紀元前251年までの治世は、実に55年。
長期政権を築きながら、地道に国内の改革を進めました。
漫画「キングダム」では、昭王は影の存在として語られています。
本編ではすでに亡くなっており、直接の登場は少ないものの、政(嬴政)や信が理想とする「中華統一」という夢の原点に位置づけられています。
特に昌文君の口から語られる昭王の理想には、作中全体のテーマが凝縮されています。
史実では、昭王が「法による国家運営」を徹底したことが、後の秦の強さを支える土台になりました。
つまり、武よりも制度。昭王は「戦の勝ち方」を作った王ではなく、「勝ち続ける国の仕組み」を作った王だったのです。
商鞅の改革がもたらした歯車の国
昭王の時代に花開いたのが、商鞅の改革でした。
商鞅が行ったのは、貴族社会を壊し、功績によって地位を決めるという革命的な仕組みです。
農業で成果を上げた者、戦場で手柄を立てた者が昇進できる。
このシステムは、血筋ではなく実力がすべてという厳しい現実を突きつけるものでした。
当時の中国では珍しく、農民でも戦功を上げれば将軍になれる可能性があったのです。
漫画「キングダム」でも、この商鞅の改革の影響ははっきり描かれています。
信が百人将、千人将と実力で地位を上げていくのは、まさに商鞅の制度そのものです。
家柄に縛られず、戦場で手柄を立てた者が上へ行く。
「戦うことで未来を掴む」という信の姿勢は、秦という国そのものの思想を体現しています。
ただし、史実の秦ではこの制度は血の制度でもありました。
一歩間違えば、失敗すれば即罰。
功績と同じくらい、失敗への罰も重く設定されていたのです。
そこには「人を甘やかさない国家」の冷たさがありました。
私がこの部分に惹かれるのは、現代社会にも似た構図があるからです。
成果主義の中で評価される人と、追い詰められる人。
秦の強さはその冷徹さの裏返しだったのかもしれません。
法家思想が作った恐れられる秩序
昭王の死後、秦を支配したのは法家思想でした。
人の善意ではなく、制度で人を動かす。
この思想を政治の中心に置いたのが、李斯をはじめとする法家の学者たちです。
法家の考えは極端です。
人間は本質的に利己的である。
だからこそ、厳しい法と罰で統制しなければならない。
李斯はこの思想を徹底的に制度化し、秦を動く機械のような国に変えていきました。
漫画「キングダム」では、昌平君がこの法家思想を象徴する存在として描かれています。
昌平君は秦の軍略を担う人物であり、同時に法と秩序を尊ぶ現実主義者です。
信や王騎が「魂の戦い」を重んじるのに対し、昌平君は「勝つための仕組み」を作る。
この対比が、物語の中での秦の冷たさと熱さの両面を際立たせています。
史実の李斯は、昭王の死後に秦の政治を支える立場となり、始皇帝の下で制度の統一を進めました。
度量衡(どりょうこう)の統一、文字の統一、法の一元化。
その全てが昭王時代の基礎の上に築かれたものです。
つまり、昭王の死後も秦が強かったのは、「仕組みが人を超えて動く国」だったから。
王が変わっても、制度が止まらない。
それが、他国にはなかった秦の恐ろしい強さでした。
昭王の軍制が作った勝ち続ける軍隊
昭王の時代、秦軍は単なる軍隊ではありませんでした。
国家そのものが戦争機構のように機能していたのです。
戦で功を立てれば褒美、失敗すれば即処罰。
兵の行動は完全に管理され、戦場では一糸乱れぬ動きを見せました。
この仕組みを完成させたのが昭王であり、実行したのが白起でした。
白起は、戦国最大の将軍です。
長平の戦いでは趙軍40万人を捕虜にし、その全員を生き埋めにしたと言われています。
残酷さの象徴のような出来事ですが、それほどの冷徹さがなければ勝ち続けることはできなかったのも事実です。
漫画「キングダム」では、白起はすでに故人として登場します。
しかし、昌平君や王翦、桓騎といった現役の将軍たちの戦い方には、どこか白起の影が見えます。
情よりも結果。
勝つためには手段を選ばない姿勢が、秦軍全体の特徴になっています。
私自身、白起という存在に複雑な感情を抱きます。
圧倒的な強さの裏に、人間としての苦しみが透けて見えるからです。
勝利を積み重ねるたびに、彼は孤独になっていったのではないか。
秦という国は、強さの代償として人間らしさを削ぎ落としていったように思えます。
「キングダム」漫画と史実の昭王の違い
昭王好きだから嬉しい⸜(*´꒳`*)⸝
髪の毛ピンクグレージュだから
桜🌸みたいだね!て言われるけど
キングダム好きの友達に
髪色蒙恬色だねて言われて
確かにっ!てなった∑( ˙ ꒳ ˙ ) pic.twitter.com/WM1NqZXYLW— てだま (@tedama1207) March 19, 2025
漫画「キングダム」での昭王は、理想を語る存在として描かれています。
人々を一つにまとめ、争いのない時代を作りたいという夢を抱いた王。
その理想を受け継ぐのが政であり、信たちの戦いの原点でもあります。
一方、史実の昭王はもっと現実的な人物でした。
民を束ねるために法を使い、国家を動かすために感情を切り捨てた。
温かみよりも合理を選んだ王です。
キングダムが史実と違うのは、理想と現実の位置づけです。
- 史実の昭王は「秩序の王」。
- 漫画の昭王は「夢の王」。
どちらも秦を強くした事実には変わりませんが、描かれ方のベクトルが違うのです。
私はこの違いを読むたびに、作者・原泰久さんの意図を感じます。
史実では冷徹な王を、物語の中では想いを残す王として描く。
それが、戦乱の物語の中に人間の希望を宿すための仕掛けなのだと思います。
「キングダム」昭王の死後、秦が最強に?
昭王が亡くなっても、国は揺るがなかった。
その理由は、昭王が作った制度があまりにも強固だったからです。
人が死んでも仕組みが動く国。
法と秩序が王の代わりになる国。
李斯や呂不韋が政治を支え、始皇帝がその果実を刈り取った。
昭王の死後に秦が最強になったのは、王の力ではなく仕組みの力だったのです。
漫画では、政が昭王の理想を引き継ぎ、「中華統一」という夢を掲げています。
史実の冷徹な制度を、人の想いに変えたのがキングダムの世界。
そこに、史実にはない温度がある。
だからこそ、読んでいて血が通っているように感じるのだと思います。
まとめ
昭王の死後、秦が最強になったのは偶然ではありません。
商鞅の改革で作られた制度が成熟し、法家思想による統制が完成し、昭王の軍制が実を結んだからです。
そしてそれを受け継いだ始皇帝が、ついに中華統一を果たした。
- 史実では冷たい合理の世界。
- 漫画では理想と情熱の物語。
どちらにも共通するのは、「人ではなく仕組みが国を動かす」という視点です。
昭王という王は、表舞台では静かでも、その影響力は計り知れない。
「キングダム」を読むとき、あの理想の言葉の裏にある現実の冷たさを知ると、物語の深みが変わります。
人の想いが国を動かすのか。
それとも制度が人を動かすのか。
昭王の死後の秦を見ると、その境界がいかに曖昧で、そして人間らしいかがわかります。
秦は最強になった。
けれど同時に、誰よりも孤独な国になっていったのかもしれません。
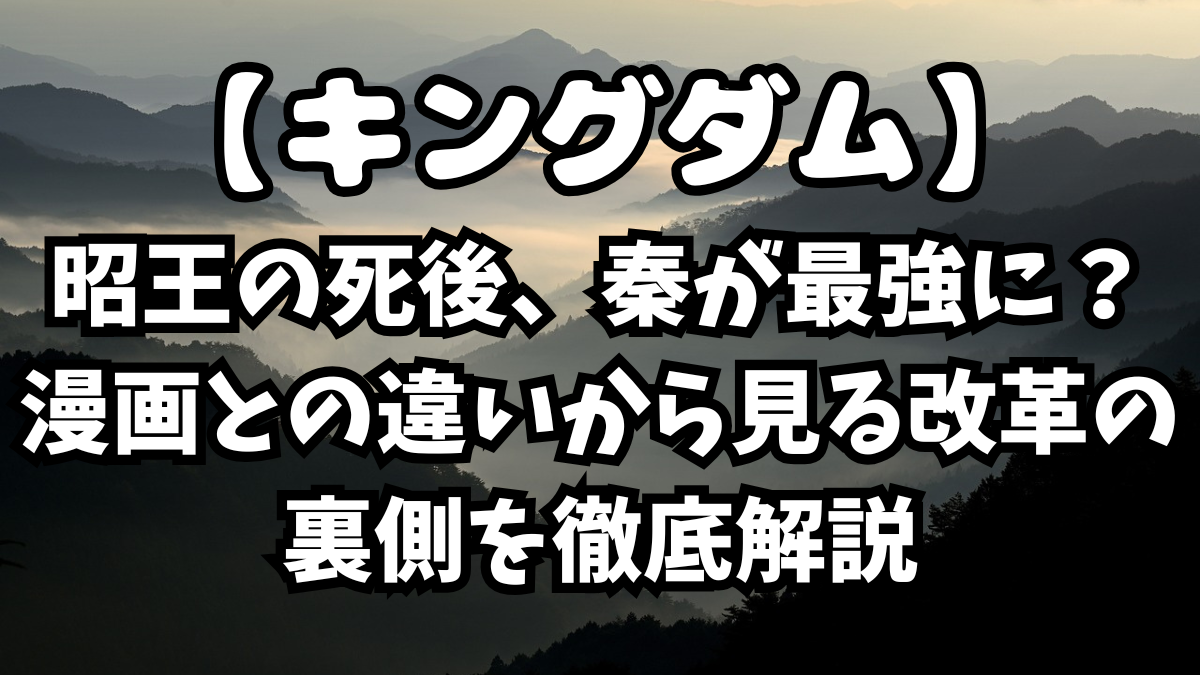


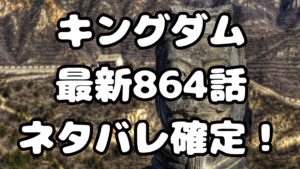
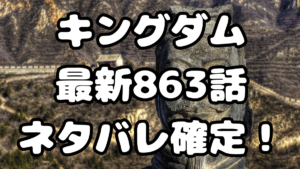
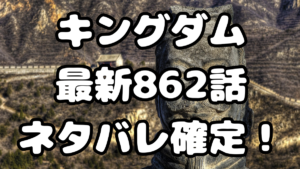
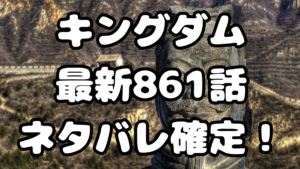
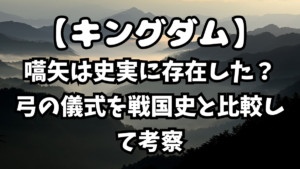
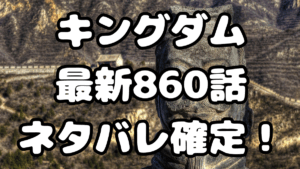
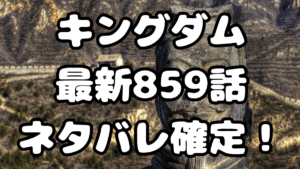
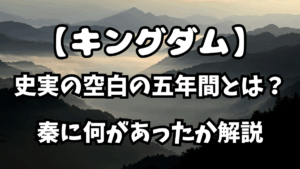
コメント