秦国の豪将・麃公が戦場に散る――。
この場面は「キングダム」の中でも屈指の名シーンとして、読者の胸を強く打ちます。
初めて読んだとき、ページをめくる手が震えたのを覚えています。
壮絶で、そしてあまりにも潔い最期でした。
今回は麃公が死んだのは何巻・何話なのか、そして史実上のモデルが存在するのかを、実際の流れをたどりながら解説します。
「キングダム」麃公とは?
キングダムなら麃公将軍。 pic.twitter.com/ilHFl7l1ks
— 残業ちゃん (@zangyo_daikirai) June 1, 2023
麃公は、戦場での勘と経験によって戦局を読む「本能型の将軍」の代表格です。
知略で戦う「知略型」の将軍が多い中、麃公は「戦の匂い」や「流れ」を肌で感じ取り、敵の意図を直感的に察知して勝利をつかむタイプです。
作中では同じく本能型の代表とされる趙国の将軍・龐煖(ほうけん)と幾度も対峙し、その激闘が物語の大きな見どころとなっています。
麃公の性格と名言
麃公は非常に豪快で、細かいことを気にしない性格です。
勝利よりも「戦そのもの」を楽しむような一面があり、部下たちからの信頼も厚い将軍です。
特に有名なのが、彼の名言:
「戦とは本能だァ!」
この言葉は、麃公の生き方そのものを象徴しています。
理屈ではなく、己の血が騒ぐままに戦場を駆ける男。
それが麃公の魅力です。
「キングダム」麃公が死亡するのは何巻の何話?
火を絶やすでないぞォ🔥❤️🔥
━━━━━━━━━━━━━━━
キングダムの麃公将軍が
頭の中を駆け抜けた夜🙄
⠀
子どもらのために、
具材の大きさや切り方考えたりして
丁寧に煮込んだ具だくさんハヤシライス。
…長女ちゃん一口も食べずに終了🫠
⠀
でもヘコんでても仕方ない!… pic.twitter.com/Pm2adXihZd— スイ | AI×副業・効率オタク (@threesisters99) September 13, 2025
麃公が戦死するのは、単行本30巻の第325話です。
合従軍編のクライマックスで、趙の三大天・龐煖との一騎打ちの末に倒れます。
読者の多くが涙した名場面といっても過言ではありません。
合従軍との戦いは、秦国の存亡をかけた一大決戦でした。
楚・趙・魏・韓・燕の連合軍が一斉に攻め込み、函谷関での防衛戦が繰り広げられます。
麃公は飛信隊と共に別働隊を率い、敵の動きを察知して行動します。
この戦で麃公は、李牧の策略にいち早く気づきました。
本能型の将として、目に見えぬ“戦の匂い”を嗅ぎ取り、誰よりも早く異変を察知します。
南道から咸陽を目指す李牧の動きを予測し、信とともに追撃に出たのです。
麃公が動かなければ、秦の都・咸陽は確実に陥落していたでしょう。
戦場を駆け抜ける麃公の姿は、まさに“野生の本能”そのものでした。
勘だけで動くようでいて、実は戦局全体を見渡している。
理屈ではなく、肌で戦を感じ取る稀有な将でした。
龐煖との戦いの結末
南道で李牧軍を追い詰めた麃公軍は、壮絶な戦闘を繰り広げます。
李牧は“流動”という独特の戦術を用い、渦のような動きで敵を飲み込みました。
大多数の兵が分断され、信たちは麃公と離れてしまいます。
それでも麃公は怯むことなく前へ進み、李牧の本陣にたどり着きました。
しかしそこに待ち受けていたのは、かつて王騎を討ち取った“武神”龐煖でした。
あの異様な存在感、静かに立っているだけで空気が張りつめるほど。
ページの向こうからでも伝わってくる緊迫感があります。
龐煖の登場によって、戦場の空気が一瞬にして変わります。
李牧の剣として現れた龐煖を見て、麃公は笑いました。
逃げるでもなく、戦略を練るでもなく、ただ戦士として対峙する。
その瞬間、すべての読者が「麃公はここで死ぬ」と悟ったでしょう。
戦いは熾烈でした。
龐煖の一撃を受けてもなお立ち上がり、麃公は何度も矛を振るいます。
体が限界を超えてもなお動き続ける姿に、武人としての意地が見えました。
麃公は龐煖の腕を折り返し、勝ちを譲らぬまま倒れていきます。
最後に信へ盾を投げ渡し、「火を絶やすでないぞ」と託す場面。あの一言の重みは、何度読んでも胸に迫ります。
個人的に印象的だったのは、龐煖が「お前は生を諦めた弱者」と言い放つ場面です。
麃公は静かに「何も分かっておらぬ」と言い返す。この短い言葉の中に、人生そのものを戦場で燃やし尽くした男の覚悟が詰まっているように感じました。
そして麃公は、龐煖の首を取ることなく散ります。
しかし、死の直前に龐煖の左腕を折ったという事実が、ただの敗北ではないことを証明しています。
命と引き換えに次の世代へ「戦の炎」を残したのです。
「キングダム」麃公の史実におけるモデルとは?
では、史実において麃公は実在したのでしょうか。
結論から言うと、正確に一致する人物は確認されていません。
史書『史記』には「麃公」という名は登場せず、架空の将軍であると考えられています。
しかし、麃公の性格や戦い方にはいくつかの実在人物の要素が混ざっているように見えます。
例えば、猛将として知られる王齕(おうこつ)や樊於期(はんおき)といった将軍の逸話が部分的に重なります。
どちらも武勇に優れ、智略よりも本能で戦うタイプとして知られていました。
麃公は“理屈より魂”の将でした。現代的な戦略思考とは正反対の存在です。
李牧のような知略型の軍師と対照的に描かれており、「理」と「本能」の対比を象徴するキャラクターでもあります。
秦の統一という大義の中で、理に押しつぶされる“野性”の最後を描くための人物ともいえるでしょう。
史実的には、戦国末期の秦軍には本能的な指揮官が多く存在したといわれます。
地形や敵の心理を読んで動く直感型の将軍たち。
麃公はそうした時代の“戦う魂”を象徴した存在だったのかもしれません。
自分が初めて麃公の死を読んだとき、単なる戦死ではなく「時代の終わり」を感じました。
理の時代が始まる直前に、本能で戦う者が去る。
まるで、古代の炎が静かに消えていくようでした。
信へ受け継がれた「矛と盾」
麃公の死後、信は麃公の盾を受け継ぎます。
王騎から受け取った矛と並び、信の戦いの象徴となる重要な装備です。
矛と盾――攻と守、理と本能、先人たちの想いを具現化したような組み合わせです。
王騎と麃公、この二人の将軍は対照的でした。
王騎は戦略と誇りの将、麃公は本能と魂の将。
それぞれが信に違う“生き様”を託します。
この二つの遺産を受け継いだ信こそが、次の時代の「中間」に立つ存在となるのです。
理も本能も併せ持つ、新たな将として。
この構図が見事に効いていると感じます。
麃公の死は悲しいけれど、決して無駄ではない。
信が成長するための通過儀礼のようなもので、物語全体の推進力にもなっています。
読者としては、あの「突撃じゃあ!」という叫びが今も耳に残ります。
豪放磊落で、戦場でこそ生きる男。
自分の命が燃え尽きるその瞬間まで、戦うことをやめなかった姿勢が、読むたびに胸を熱くします。
まとめ
麃公が戦死するのは単行本30巻・第325話です。
龐煖との壮絶な一騎打ちの末、盾を信に託して散ります。
李牧の侵攻を見抜き、戦局を動かした本能型の将として、麃公の存在は物語の中でも特別な意味を持っています。
史実上のモデルは存在しないものの、その生き様は古代の猛将たちを彷彿とさせます。
麃公は理ではなく「本能」で戦った最後の男。信に盾を託した瞬間、王騎からの矛とともに、過去から未来へと“炎”が渡されたのです。
キングダムを読み返すたびに、麃公の死は新しい意味を帯びて見えてきます。
戦で散った一人の将軍としてではなく、信の原点として、そして秦の魂の象徴として。
「火を絶やすでないぞ」という言葉が、今もページの中で燃え続けているように思います。
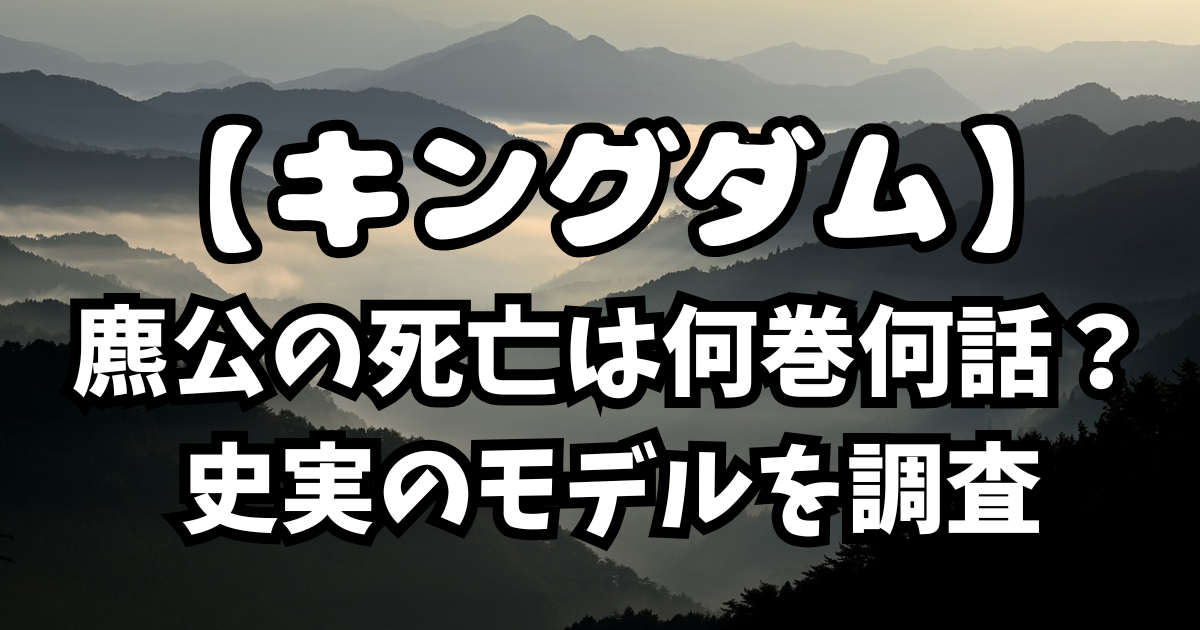


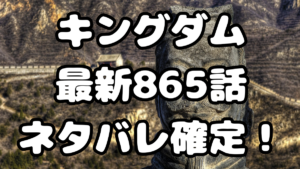
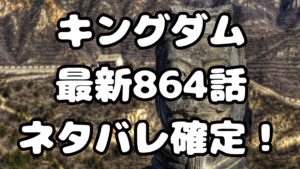
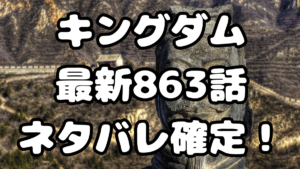
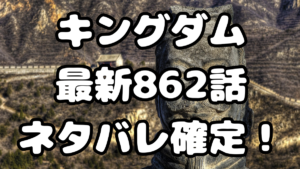
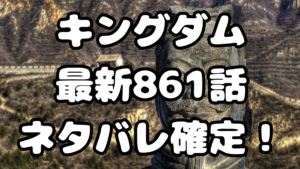
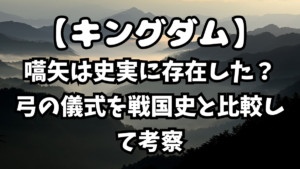
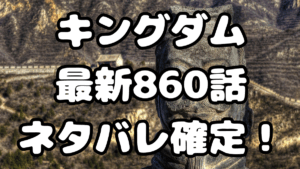
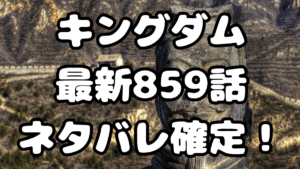
コメント